|
2025,10,26, Sunday
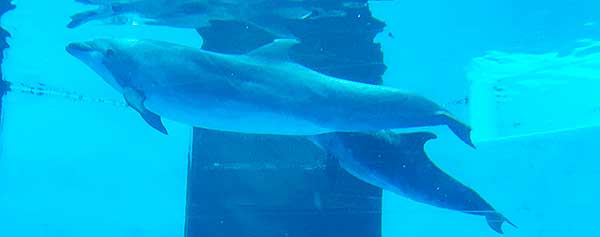 毎年参加している日本全国規模の日本SF大会とは別に、SFファンの世界には「地方コンベンション」と呼ばれるものがたくさんあって、私は愛知県の『DAINA??CON』と島根の『雲魂』によく参加しています。どちらも、ほぼ固定した参加者が年に一度集まるイベントになっています。 今回は愛知県日進市で開催される『DAINA??CON』に参加するために名古屋に行き、会場に行く前に立ち寄った名古屋港水族館をご紹介します。 名古屋港水族館には初めてではなく、以前は2019年潜水艦救難艦ちよだ一般公開に行ってきたの時にも入っています。 同じ名古屋港内には先先代の南極観測船「ふじ」なども展示されています。  これらの水槽は屋上の大プールに繋がっていて、いわゆるイルカショーも行われています。私はイルカショーには否定的なのでこちらは見ずにもう一つの呼び物であるクジラ類の遠い祖先の復元骨格標本を見に行きました。  クジラはもともと陸上に暮らしていたパキケトゥスというオオカミに似た動物が徐々に水中生活に順応していったと考えられていて、そのパキケトゥスから現在のクジラ類に至る様々な化石が発見されています。その復元骨格標本が、常設でこんなにたくさん見られるのは、たぶんここだけ。  そのパキケトゥスからさらに少し水中向けの適応が強まったのがこちらのアンブロケトゥス。まだ立派な後肢があり、陸上でも生活できたと考えられています。  その後、後肢がなくなって完全に水中生活するようになったバシロサウルス。発見時は爬虫類(魚竜)の仲間だと推定されたために「サウルス」の名がついていますが、哺乳類です。 水中生活をするにはこの形態がいちばん都合が良いようで、クジラ・イルカの仲間の海棲哺乳類だけではなく、サメの仲間も、絶滅した海棲爬虫類(魚竜やモササウルス類)も似たような形態に進化しています。この現象を収斂進化と言います。人類が作った潜水艦も同じような格好をしていることからも、水中ではこの形が理想的なのでしょう。  同じバシロサウルス類で少し小型のジゴリーザ。この化石を見ると、この段階で後ろ脚がなくなっていることがわかります。  南館に移ると、魚類やペンギンやウミガメの展示もあります。普通の水族館ですね。ここのペンギンは空調の効いた室内での展示で、いろんな種類がまとまって入れられています。  その南館に館内レストランがあって。そこでは一風変わったメニューとしてサメやワニの肉を使用した料理が提供されています。 その南館に館内レストランがあって。そこでは一風変わったメニューとしてサメやワニの肉を使用した料理が提供されています。サメは近縁種のエイ肉を何度か食べているので、今回はクロコダイルカレーを選択しました。 カレーの上にワニ肉のフライが載っています。 ワニ肉は「すごく噛み応えのある鶏肉」という感じの味わいでした。ヘビ肉も鶏肉に近い味だと聞いているので、爬虫類全般にそういう傾向なのかもしれません。 さて、名古屋港水族館に来たらもう一つ見ておきたいところがあります。 続き▽
| https://blog.tsuduki.com/index.php?e=612 |
| お仕事(小説/SF) | 04:49 PM | comments (0) | trackback (x) | |
|
2025,10,05, Sunday
 10月最初の日曜日、前日から続く小雨がそぼ降る中朝から琵琶湖で外来魚駆除のイベントに参加してました。 春にも参加したのですが、この時はイベント全体でほとんど釣れず、私自身も国内外来魚(日本に昔からいる淡水魚ではあるけど、琵琶湖にはいなかった魚)のヌマチチブが2匹、という結果でした。 そんなわけで、どうにか都合のつくこの日にリベンジと思って参加してきたわけです。 なお今回釣った魚を撮影しただけで周囲の状況は撮らなかったので、現場の雰囲気は春のイベントの時のものを参照してください。 今回は朝7時頃から12時頃まで釣って、ブルーギル4匹とブラックバス1匹を釣りました。  最初に釣れたのは小さいブルーギルでした。今回から「お魚観察アクリル水槽」を買ったので、針を外す前にそこに入れて撮影しています。 最初に釣れたのは小さいブルーギルでした。今回から「お魚観察アクリル水槽」を買ったので、針を外す前にそこに入れて撮影しています。体長8cmほど。綺麗な、そして典型的な縞模様のブルーギルの幼魚でした。 アタリはほぼ感じ取ることができず、水草の塊に仕掛けが入っていきそうになったので根掛かりを避けるために引き上げたらかかっていました。 2番目に釣れたのはページトップにあるブラックバスの幼魚です。体長13cm。小さくてもさすがブラックバス。アタリもはっきりして横向きにひったくるように走ってくれました。稚魚じゃなく幼魚と言えるサイズのバスを釣ったのはこれが初めてです。  3番目に釣れたのは少しマシなサイズの体長12cmのブルーギル。こちらも綺麗な縞模様ですね。  次に釣れたのもほぼ同じサイズのブルーギル。体色が違うのは、生活環境の違いですかね。  お昼ご飯を食べた後、雨が強くなってきてそろそろ止めようかなと思いかけた時に釣れた最後の1匹も、同サイズのブルーギル。 雨が降ったりやんだりの中、アタリは多かった(ウキがもぞもぞ動くだけの控えめなアタリはたぶん在来魚ですが)し一度は針に掛けたのにバラした(ブルーギル1、バス1は魚体が見えるところまではきました)のも多かったので全体に活性は高かったかと。 イベント全体でも今日はバスがたくさん釣れてました。イベント主催者の発表でも、全体で5.6kgの駆除、匹数の8割がブラックバスだったそうです。 昨年まではほぼブルーギルしか釣れず、春はほとんど釣れなかったのに、今年の春以降に急にブラックバスが増えたのは、なんか奇妙な気がします。 |






