|
2024,05,29, Wednesday
 他の水族館の例に漏れず、海遊館も生態系の維持のためにいろんな仕事をしているわけですが、その一環として大阪湾のスナメリ(小型の鯨類)の生息調査を行うにあたり、一般参加を募集しているというのを公式サイトで見つけまして、参加してきました。 当日は朝に集合、1時間ほど海遊館内で大阪湾とスナメリについてのレクチャーを受け、乗船。関西空港の周囲をメインにスナメリを探し、14時ごろに海遊館で解散。というスケジュールです。 気温は陸上ならすでに半袖でも十分な時期ですが、海の上は気温が低いし風が吹くこともあるので長袖・上着も持参するように連絡がありました。私は雨具と兼用のレインスーツを上だけバッグの中に突っ込んで行きました。 他に用意したのは双眼鏡と偏光サングラス。念の為、集合時間の直前に酔い止めの薬も飲んでおきました。※船が小さいと大阪湾内でもそれなりに揺れることがあるし、大型のフェリーを除けば10年以上乗っていないので、本当に念の為。 レクチャーは大阪湾で行われている生物多様性再生の取り組みの話と、今回の目的であるスナメリを探す時のポイントなど。その後、海遊館のすぐ裏手にある桟橋から船に乗り込みます。  小さい釣船みたいなのが来たらまずいと思って酔い止めの薬まで飲んでいたのですが、用意されていたのは50人は乗れそうな双胴船。考えてみれば一般参加が15人と学生15人、海遊館からのスタッフも数名乗り込むのだから、そんな小さな船が来るわけがなかったのでした。キャビンの上(画像の操縦室のすぐ後ろ)がデッキになっていて、一般参加と学生とが30分交代でそこからスナメリを探します。 出航してすぐ、走る船を避けて逃げる魚がたくさんいることに気が付きます。水面スレスレ、時にはジャンプもする。黒い背中に腹側は白っぽい。魚体の形から、堤防釣りで見慣れたボラだとわかりました。 ボラ、沿岸部に集まる魚だと思っていましたが、大阪湾中にウヨウヨいるんですね。驚きました。 スナメリの目撃は関西空港の周辺で多いということで、30分交代の2回目の捜索に期待しましたが、やはり見えず。通常は目視で広い範囲を探り、怪しいものが見えたら双眼鏡を使うという方法を取っていたのですが、見つかるのは流木やゴミばかり。スナメリは背鰭がなく水上では黒っぽい色なので海面の波と見分けがつきにくいと教わってはいましたが、想像以上に難しかったです。 そうこうしているうちにトビウオがいる海域に入ったようで、何匹か空中を飛ぶ姿を見ることができました。 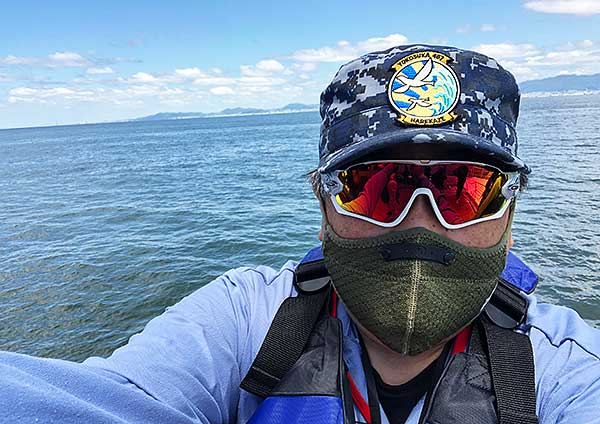 同乗していた人たちからは何度か「見つけた」という声が上がっていたのですが私自身はスナメリを見ることはできず、海遊館のスタッフの方が撮影した画像を見せてもらえたくらいでした。目視で探すのがこれだけ難しいと、一回の調査でわかることはほとんどなく、期間的にも回数的にもたくさんのデータを積み重ねてはじめて「生息数」といった具体的な数字ではなくて「生息数の増減」くらいの情報がわかるくらいなのだろうな。ということも実感。長期的に続ける必要のある調査だと思いました。 大阪湾の水質はゆっくりではありますが回復しています。それは堤防から釣りをしているだけでも実感できることですが、富栄養化や逆に貧栄養化が起こるなど、まだまだ海の環境に人間がどんな影響を及ぼしているのか、継続的に調査しなければいけないことではあるので、こうした地道な調査は続けていってもらいたいと思います。 |
|
この記事に対するコメントの受付は終了しています。
コメント
|






